
|
 |
 |
 |
 第5回 第5回 |
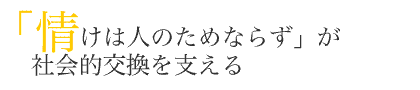 |
 文学研究科行動システム科学講座准教授 高橋伸幸 文学研究科行動システム科学講座准教授 高橋伸幸 |
|
 
 |
| -- |
「社会的交換」とは何ですか? |
 |
 |
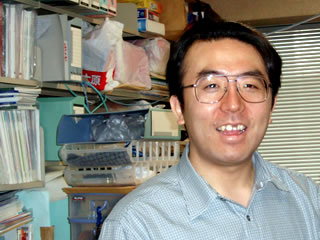 交換と聞いてまず思い浮かぶのは経済的交換ではないでしょうか?経済的交換はお金そのものや、金額に換算できるものの交換で、一回きりで完結するのが特徴です。人間社会で広く行われる社会的交換では、金額に換算できないもの、友情や愛情、情報、尊敬などを交換し、それも比較的長くやり取りします。たとえば、入学祝いとかね。交換されるものをまとめて「資源」と呼びます。 交換と聞いてまず思い浮かぶのは経済的交換ではないでしょうか?経済的交換はお金そのものや、金額に換算できるものの交換で、一回きりで完結するのが特徴です。人間社会で広く行われる社会的交換では、金額に換算できないもの、友情や愛情、情報、尊敬などを交換し、それも比較的長くやり取りします。たとえば、入学祝いとかね。交換されるものをまとめて「資源」と呼びます。 |
 |
| -- |
社会的交換はどのように行われるのですか? |
 |
 |
交換のかたちにもいろいろあります。動物にも見られる一対一の交換は、一方が提供すればもう一方がお返しをするという“持ちつ持たれつ”の関係で、「直接交換」と呼ばれます。しかし、人間社会で行われている交換はこれだけではありません。「一般交換」と呼ばれる交換は一対一で行われるものではなく、多人数の間で行われます。たとえば、まずAさんがBさんに一方的に資源を提供します。Bさんは必ずしもAさんにお返しをするのではなく、同じように誰かに一方的に資源を提供します。それを受けた人も誰かに提供し・・・と全員が一方的に資源を提供しあう状態ができていれば、Aさんもいずれ誰かに提供してもらえるでしょう。いわゆる“情けは人のためならず”ですね。これは人間に特有の行動で、チンパンジーですら行わないとされています。 |
 |
| -- |
一方的な提供にはリスクがあるように思えます |
 |
 |
一方的な資源の提供に対してちゃんとお返しがある、というシステムができていれば一般交換はずっと続いていくはずです。 ただし、誰彼かまわずやみくもに提供していると、自分は提供せずにもらうだけの、「ただ乗り」する人が現れる可能性があります。すると、提供するという流れが途切れますから、一般交換のシステムは壊れてしまいます。では、なぜ一般交換が成立し、続いていくのでしょう。人間が「相手をいい人だと判断すれば資源を提供するし、悪い人だと判断すれば提供しない」という条件つきの行動パターンを持っていると考えれば説明がつきます。私たちは、“こういう条件で行動すれば理論的に一般交換が成立するはず”というモデルパターンを計算で求め、それが実際の人間の行動と一致するかどうかを確かめる実験を行いました。 |
 |
| -- |
計算ではじき出されたモデルと実験の結果は一致しましたか? |
 |
 |
計算の結果、一般交換が続くためのモデルパターンは
|
| 1. |
「よい人」に提供した人は「よい人」だから、自分も提供する |
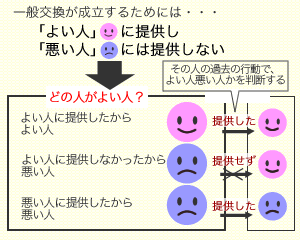 |
| 2. |
「よい人」に提供しなかった人は「悪い人」だから、自分は提供しない |
3.
|
「悪い人」に提供した人は「悪い人」だから、自分は提供しない |
というものでした。 “「悪い人」に提供した人は「悪い人」”と判断するのが特徴です。これは実際に人間の行動を調べた実験の結果と一致しました。 |
 |
| -- |
この研究をどのように発展させますか? |
 |
 |
これまでは集団内での個人間の交換を考えてきました。次に考えたいのは「個人と集団」の間の交換についてです。この場合は、集団のために働く人が「よい人」と見なされるのかもしれません。昔から社会には、たとえば田んぼに水を引くなど協同で解決しなければならない問題がありました。力を合わせればうまくいくとわかっていても、人に任せて自分は楽をしたい=ただ乗りしたいのが人間です。地球温暖化もこれと同じような問題ですが、効果的な解決策はなかなか見つからない。
一般交換の考え方では「悪い人」に資源を提供しません。提供しないという行動は悪い人への罰になりますが、積極的に攻撃を加えるわけではなく、単に何もしないだけです。だから、罰を与える側の人には特に負担がない。これを個人と集団の間の交換に応用すれば、協同で解決しなければならない問題への対処法が見えてくるかもしれません。 |
 |
 |
メモ |
 |
 |
他己紹介 |
 |
高橋先生とは分野は違えど、交換に対して同じような関心を持っているようです。次々に前の人を紹介していくというのはまさに「一般交換」ですし、共同研究というものも「情けは人のためならず」の原理に支えられていますね。
(経済学研究科現代経済経営専攻 西部 忠) |
|
|
|

