|
ワークショップ一覧
The 4th CEFOM/21 International Symposium
Cultural and Adaptive Bases of Human Sociality
日時:2006年9月9日(土)〜10日(日)
於:国際文化会館(東京・六本木)
スピーカー:
Mary C. Brinton (社会学、ハーバード大学)
Leda Cosmides (進化心理学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校)
Joseph Henrich (進化人類学、ブリティッシュコロンビア大学)
Yoshihisa Kashima (社会心理学・文化心理学、メルボルン大学)
Shinobu Kitayama (文化心理学、ミシガン大学)
山岸俊男 (社会心理学、北海道大学)
亀田達也 (社会心理学、北海道大学)
他、参加者約130名
第4回国際シンポジウムの目的は、文化、生態、制度などをキーワードとした諸分野で先端的な研究を行っている海外の第一線の研究者、またこうした諸分野で活躍されている国内の研究者に話題提供を行っていただくことで、新たな学問的融合を生み出すきっかけとなる場を設けることにあった。東京近郊のみならず全国から多数の参加者が来場し、本シンポジウムに対する関心の高さがうかがわれた。そして発表者とフロアーとの間では白熱した議論が展開され、極めて盛況なシンポジウムであった。
シンポジウムでは、社会学、進化心理学、進化人類学、文化心理学、社会心理学等を専門とする研究者による講演、大学院生を含めた国内研究者によるによる口頭、ポスター発表が行われた。そこで取り上げられた話題は、「社会的交換における認知適応」、「文化的集団選択」、「日本の労働市場における、若者の選好」などであった。
* シンポジウムのプログラムはこちらから
第1日目 2006年9月9日(土)
ご挨拶 (9:30-9:40)
山岸俊男(北海道大学)
"Welcome and Introduction."

口頭発表#1 (9:40-11:00)
渡部 幹 (京都大学)
"Cultural difference of resource distribution and opportunity costs."
 発表では、日米における資源配分の仕方と社会的流動性の差異について議論された。まず、日米において最後通牒ゲームを行ったところ、日本人のほうがアメリカ人よりも、自分は多く受け取り相手にはあまり渡さないという分配選択を選びやすいことがわかった。しかし、相手が良い人物であることがわかる条件では、このパターンは逆になり、むしろアメリカ人のほうがアンフェアな選択をした。加えて、コンピュータ・シミュレーションの結果、社会的流動性の差がこうした資源配分の差異に影響を与えていることが示された。具体的には、社会的流動性の低い社会(例えば日本社会)では、一度関係ができるとそれに固執するほうが適応的であるがゆえに、見知らぬ人間にはアンフェアにふるまう一方、良い人間であればフェアにふるまうことによってその関係を維持しようとするのに対し、社会的流動性に高い社会(例えばアメリカ社会)では、機会コストが大きいために、見知らぬ人にフェアにふるまうことで関係を作ると同時に、良い人に対してアンフェアにふるまっても新たなパートナーを見つけることが可能であることが示唆された。
発表では、日米における資源配分の仕方と社会的流動性の差異について議論された。まず、日米において最後通牒ゲームを行ったところ、日本人のほうがアメリカ人よりも、自分は多く受け取り相手にはあまり渡さないという分配選択を選びやすいことがわかった。しかし、相手が良い人物であることがわかる条件では、このパターンは逆になり、むしろアメリカ人のほうがアンフェアな選択をした。加えて、コンピュータ・シミュレーションの結果、社会的流動性の差がこうした資源配分の差異に影響を与えていることが示された。具体的には、社会的流動性の低い社会(例えば日本社会)では、一度関係ができるとそれに固執するほうが適応的であるがゆえに、見知らぬ人間にはアンフェアにふるまう一方、良い人間であればフェアにふるまうことによってその関係を維持しようとするのに対し、社会的流動性に高い社会(例えばアメリカ社会)では、機会コストが大きいために、見知らぬ人にフェアにふるまうことで関係を作ると同時に、良い人に対してアンフェアにふるまっても新たなパートナーを見つけることが可能であることが示唆された。
清成 透子 (マクマスター大学)
"Punishing non-cooperators
doesn't yield a solution to the problem of cooperation but rewarding cooperators
does."
 血縁関係のない集団における人々の協力行動がなぜ可能なのかは、古くから議論されてきている。それを可能にする1つの説として罰の効力が挙げられる。しかし、罰の行使そのものにコストがかかるため、実際のところこれ自体が公共財問題といえる。よって、非協力者を罰しない人を罰するかという問題が生じる。発表では、この点を検証するために日本およびカナダで行われた実験が紹介された。そして1回限りの社会的ジレンマ状況では、人々は実際には非協力者を罰しなかった人をほとんど罰しないことが示された。しかしながら、逆に協力者に報酬を与えた人に報酬を与えるかどうかを同様の実験状況でみたところ、その割合は大きく増えた。このことから、報酬による肯定的なフィードバック(つまり間接互恵性)が血縁関係のない集団の協力行動を可能にする1つのキーファクターとなっていることが示唆された。
血縁関係のない集団における人々の協力行動がなぜ可能なのかは、古くから議論されてきている。それを可能にする1つの説として罰の効力が挙げられる。しかし、罰の行使そのものにコストがかかるため、実際のところこれ自体が公共財問題といえる。よって、非協力者を罰しない人を罰するかという問題が生じる。発表では、この点を検証するために日本およびカナダで行われた実験が紹介された。そして1回限りの社会的ジレンマ状況では、人々は実際には非協力者を罰しなかった人をほとんど罰しないことが示された。しかしながら、逆に協力者に報酬を与えた人に報酬を与えるかどうかを同様の実験状況でみたところ、その割合は大きく増えた。このことから、報酬による肯定的なフィードバック(つまり間接互恵性)が血縁関係のない集団の協力行動を可能にする1つのキーファクターとなっていることが示唆された。
清水 和己 (早稲田大学)
"Group affiliation
and 'altruistic' punishment: Who provides 'altruistic' punishment?"
 発表では、利他的な罰を行使するにあたっての人々の心理プロセスの諸側面(例えば公平さ)および人々の集団所属性の影響を見るために行われた資源提供ゲームの実験結果が報告された。参加者の公平性のプロフィールと資源提供ゲームにおけるフリーライダーへの罰の行使率との相関を見たところ、フリーライダーの集団所属性にかかわらず、公平性の高い人々ほど罰を行使する傾向が見られた。加えて事後質問紙の結果から、資源提供ゲームにおいて協力傾向の高かった人ほど、そして公平性が高かった人ほど、フリーライダーを罰する人を支持する傾向が見られた。
発表では、利他的な罰を行使するにあたっての人々の心理プロセスの諸側面(例えば公平さ)および人々の集団所属性の影響を見るために行われた資源提供ゲームの実験結果が報告された。参加者の公平性のプロフィールと資源提供ゲームにおけるフリーライダーへの罰の行使率との相関を見たところ、フリーライダーの集団所属性にかかわらず、公平性の高い人々ほど罰を行使する傾向が見られた。加えて事後質問紙の結果から、資源提供ゲームにおいて協力傾向の高かった人ほど、そして公平性が高かった人ほど、フリーライダーを罰する人を支持する傾向が見られた。
竹澤 正哲 (ティルバーグ大学)
"Revisiting
'The evolution of reciprcity in sizable groups' "
 古くから互恵性によって二者間の囚人のジレンマゲームにおける協力行動は進化するとされてきた。加えて、n人の囚人のジレンマゲームにおいても、互恵的な行動はしばしば報告されている。しかしBoyd & Richersonは、互恵性では囚人のジレンマゲームにおける協力行動を説明することができないと主張している。発表では、このBoyd & Richersonのモデルにおける互恵性がトリガー戦略になっていることを指摘し、代わりに連続的互恵戦略(他のメンバーの平均協力率に合わせて、自らの協力行動を決定する戦略)を投入すると、N=100を超えるようなグループサイズを想定した場合でも互恵的な協力行動が進化することが示唆された。
古くから互恵性によって二者間の囚人のジレンマゲームにおける協力行動は進化するとされてきた。加えて、n人の囚人のジレンマゲームにおいても、互恵的な行動はしばしば報告されている。しかしBoyd & Richersonは、互恵性では囚人のジレンマゲームにおける協力行動を説明することができないと主張している。発表では、このBoyd & Richersonのモデルにおける互恵性がトリガー戦略になっていることを指摘し、代わりに連続的互恵戦略(他のメンバーの平均協力率に合わせて、自らの協力行動を決定する戦略)を投入すると、N=100を超えるようなグループサイズを想定した場合でも互恵的な協力行動が進化することが示唆された。
講演1 (11:10-11:40)
亀田 達也 (北海道大学)
"Democracy under
uncertainty: Adaptive robustness of group decision-making beyond the voter's
pradox."
 集団による意思決定は、どの人間社会においても幅広く見られる普遍的現象である。その適応基盤として、多くの知識が集積される結果、集団は個人と比べて優れた決定を下しやすいことが指摘されている。しかし、不確実状況下における集団の意思決定では、正確な知識の獲得行動(情報探索)や表出行動(投票)には個人的なコストがかかり、「投票者のパラドクス」という政治学の概念で総括されるようなフリーライダー問題を孕むことになる。発表では、フリーライダー問題があるにもかかわらず、多数決による集団意思決定は機能するのかどうかを検討したコンピュータ・シミュレーションと行動実験が報告された。シミュレーションでは、フリーライダー問題を孕んでいても、集団意思決定を採択する母集団内では、協力者と非協力者が共存するような混合均衡が一般的に成立することが示された。加えて、幅広いパラメタの範囲で、多数決はベストメンバーによる独裁(協力者の間で最も有能な個人の意思決定に常に従う)に比べ、より効率的な意思決定手段であることが示された。さらに、インタラクティブな集団による行動実験により、これらの命題の正しさが経験的に確認された。
集団による意思決定は、どの人間社会においても幅広く見られる普遍的現象である。その適応基盤として、多くの知識が集積される結果、集団は個人と比べて優れた決定を下しやすいことが指摘されている。しかし、不確実状況下における集団の意思決定では、正確な知識の獲得行動(情報探索)や表出行動(投票)には個人的なコストがかかり、「投票者のパラドクス」という政治学の概念で総括されるようなフリーライダー問題を孕むことになる。発表では、フリーライダー問題があるにもかかわらず、多数決による集団意思決定は機能するのかどうかを検討したコンピュータ・シミュレーションと行動実験が報告された。シミュレーションでは、フリーライダー問題を孕んでいても、集団意思決定を採択する母集団内では、協力者と非協力者が共存するような混合均衡が一般的に成立することが示された。加えて、幅広いパラメタの範囲で、多数決はベストメンバーによる独裁(協力者の間で最も有能な個人の意思決定に常に従う)に比べ、より効率的な意思決定手段であることが示された。さらに、インタラクティブな集団による行動実験により、これらの命題の正しさが経験的に確認された。
口頭発表#2 (13:10-14:50)
真島 理恵 (北海道大学)
"Is the enemy's
friend an enemy? An experimental study to examine strategies in indirect reciprocity
settings."
 間接互恵性が成り立つためには、パートナーの前回の行動(一次情報)のみならず、パートナーの前回の相手の評判(二次情報)を考慮する必要があることが知られている。先行研究によれば、良い評判の人に提供した人を「良い」とし、一方、良い評判の人に提供しなかった人を「悪い」と評価することに加え、悪い評判の人に提供した人を「悪い」と評価することが間接互恵性の成立の前提となっている。発表では、実際に人々は、悪い評判の人に提供した人を「悪い」と評価するのかどうかを調べるために行った実験が紹介された。参加者は資源提供ゲームに参加し、各参加者の一次情報、二次情報を見ることができた。そして実際に参加者がこのような選別戦略をとっているのかを見るため、参加者がどのタイプの参加者を選んで提供したかを調べたところ、予測と一致し、非提供者に提供した人を好む割合は、提供者に提供した人を好む割合よりも低くなっていた。
間接互恵性が成り立つためには、パートナーの前回の行動(一次情報)のみならず、パートナーの前回の相手の評判(二次情報)を考慮する必要があることが知られている。先行研究によれば、良い評判の人に提供した人を「良い」とし、一方、良い評判の人に提供しなかった人を「悪い」と評価することに加え、悪い評判の人に提供した人を「悪い」と評価することが間接互恵性の成立の前提となっている。発表では、実際に人々は、悪い評判の人に提供した人を「悪い」と評価するのかどうかを調べるために行った実験が紹介された。参加者は資源提供ゲームに参加し、各参加者の一次情報、二次情報を見ることができた。そして実際に参加者がこのような選別戦略をとっているのかを見るため、参加者がどのタイプの参加者を選んで提供したかを調べたところ、予測と一致し、非提供者に提供した人を好む割合は、提供者に提供した人を好む割合よりも低くなっていた。
中丸 麻由子 (東京工業大学)
"The coevolution
of altruism and punishment: Role of the selfish punisher."
 利他的行動と罰行動との関係を調べるために、1)非協力者を罰する協力者(AP)、2)非協力者を罰しない協力者(AN)、3)非協力者を罰する非協力者(SP)、4)非協力者を罰しない非協力者(SN)の戦略に注目した数理モデルについて報告された。発表では、とりわけSPに注目し、Fertility model(ある個体はランダムに死ぬが、しかし発生率は戦略の強さに依存)とViability model(戦略の強さは個体が死ぬ程度に影響を与えるが、発生率はランダム)において、SPによる協力行動へのインパクトについて議論された。結果は、後者においてのみSPは、APの増加に寄与していた。さらに、両方のモデルともに、個体が隣接する4個体としかやりとりできないlattice構造の場合には、SPがAPの増加に寄与するだけなく、結果的にANが減少しその結果としてAPが増加する傾向も見られた。
利他的行動と罰行動との関係を調べるために、1)非協力者を罰する協力者(AP)、2)非協力者を罰しない協力者(AN)、3)非協力者を罰する非協力者(SP)、4)非協力者を罰しない非協力者(SN)の戦略に注目した数理モデルについて報告された。発表では、とりわけSPに注目し、Fertility model(ある個体はランダムに死ぬが、しかし発生率は戦略の強さに依存)とViability model(戦略の強さは個体が死ぬ程度に影響を与えるが、発生率はランダム)において、SPによる協力行動へのインパクトについて議論された。結果は、後者においてのみSPは、APの増加に寄与していた。さらに、両方のモデルともに、個体が隣接する4個体としかやりとりできないlattice構造の場合には、SPがAPの増加に寄与するだけなく、結果的にANが減少しその結果としてAPが増加する傾向も見られた。
山形 伸二 (東京大学)
"Cross-cultural
differences in heritability of personality traits: Using behavioral genetics
to study culture."
 発表では、パーソナリティーへの遺伝的および環境的影響の強さに関して、カナダ、ドイツ、日本で行われた研究が紹介され、カナダ、ドイツと比べ、日本における遺伝によるパーソナリティーへの影響は弱いことが示唆された。その理由として、日本では民族的に遺伝子の個人間の差異が小さい可能性、集団主義の強いアジアでは、状況や周囲の人間関係が行動に対して相対的に強い影響を与えている可能性が考えられ、これらの可能性を検証するため、今後の課題として他のアジア諸国における今回の結果の追試、日本国内における集団主義文化の強さとの関連の検討などが提起された。
発表では、パーソナリティーへの遺伝的および環境的影響の強さに関して、カナダ、ドイツ、日本で行われた研究が紹介され、カナダ、ドイツと比べ、日本における遺伝によるパーソナリティーへの影響は弱いことが示唆された。その理由として、日本では民族的に遺伝子の個人間の差異が小さい可能性、集団主義の強いアジアでは、状況や周囲の人間関係が行動に対して相対的に強い影響を与えている可能性が考えられ、これらの可能性を検証するため、今後の課題として他のアジア諸国における今回の結果の追試、日本国内における集団主義文化の強さとの関連の検討などが提起された。
石井 敬子 (北海道大学)
"Culture and perceputural
inference: inferring the identity of an object from its parts or its blurred
image."
 近年の文化心理学の研究では、西洋においては分析的思考が優勢であるのに対し、東洋においては包括的思考が優勢であるとされている。発表では、こうした文化差が果たして知覚的推論においても生じるかどうかを検討した実験が紹介された。参加者は、画像の一部が見える場合(パーツ)と、画像をぼやかした場合(モザイク)の2種の写真を提示され、その元の画像が何であるかを推測するよう求められた。パーツの場合には、部分の情報に注意を向け、それを元に全体像を推測しなければならないことを反映し、参加者の正答率を見たところ、ヨーロッパ系アメリカ人のほうが日本人およびアジア系アメリカ人よりも高くなっていた。一方、モザイクの場合には、全体に対して包括的に注意を向けた上で全体像を推測しなければならないが、実際のところ文化差は見られなかった。発表では、包括的注意を検出するための条件について議論された。
近年の文化心理学の研究では、西洋においては分析的思考が優勢であるのに対し、東洋においては包括的思考が優勢であるとされている。発表では、こうした文化差が果たして知覚的推論においても生じるかどうかを検討した実験が紹介された。参加者は、画像の一部が見える場合(パーツ)と、画像をぼやかした場合(モザイク)の2種の写真を提示され、その元の画像が何であるかを推測するよう求められた。パーツの場合には、部分の情報に注意を向け、それを元に全体像を推測しなければならないことを反映し、参加者の正答率を見たところ、ヨーロッパ系アメリカ人のほうが日本人およびアジア系アメリカ人よりも高くなっていた。一方、モザイクの場合には、全体に対して包括的に注意を向けた上で全体像を推測しなければならないが、実際のところ文化差は見られなかった。発表では、包括的注意を検出するための条件について議論された。
竹村 幸祐 (北海道大学)
"Tow types of
collectivism: Intragroup relationship orientation in Japan and intergroup comparison
orientation
in the United States."
 集団状況での行動傾向や心理過程に関する近年の比較文化研究により、東アジアと北米では集団主義の「タイプ」が異なるという仮説が提唱されている。発表では、特に、東アジアでは内集団のメンバー間の関係が注目されやすいのに対し、北米では内外集団の優劣関係が注目されやすいという仮説を検証した2つの日米比較研究が紹介された。研究1では自己評価型の質問紙尺度を用いて、日本人とアメリカ人の集団状況における志向性が測定され、研究2では記憶課題を用いた実験室実験を通じて日本人とアメリカ人の志向性が測定された。いずれの研究でも仮説を支持する結果が得られ、日本人は内集団メンバー間の関係に注意を払い、アメリカ人は内外集団間の関係に注意を払う傾向を持っていることが示された。最後に、こうした日米差は、社会関係の流動性や資源獲得競争の激烈さにおける日米差と関係しているという解釈が提出された。
集団状況での行動傾向や心理過程に関する近年の比較文化研究により、東アジアと北米では集団主義の「タイプ」が異なるという仮説が提唱されている。発表では、特に、東アジアでは内集団のメンバー間の関係が注目されやすいのに対し、北米では内外集団の優劣関係が注目されやすいという仮説を検証した2つの日米比較研究が紹介された。研究1では自己評価型の質問紙尺度を用いて、日本人とアメリカ人の集団状況における志向性が測定され、研究2では記憶課題を用いた実験室実験を通じて日本人とアメリカ人の志向性が測定された。いずれの研究でも仮説を支持する結果が得られ、日本人は内集団メンバー間の関係に注意を払い、アメリカ人は内外集団間の関係に注意を払う傾向を持っていることが示された。最後に、こうした日米差は、社会関係の流動性や資源獲得競争の激烈さにおける日米差と関係しているという解釈が提出された。
ポスター発表#1 (14:50-15:50)
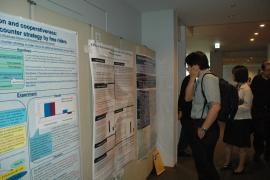 
明地 洋典 (東京大学)
"Effects of gaze direction on the processing of threat-related facial expression
in children with autism and without autism."
平石 界 (東京大学)
"Universals and differences: What can we expect by bridging evolutionary psychology and behavioral genetics?"
堀田 結孝 (北海道大学)
"Inequity enhancing rejection of unfair offers in ultimatum games."
井上 由美子 (井之頭病院)
"Deficit in theory of mind is a risk for relapse of major depression."
犬飼 佳吾 (北海道大学)
"Generalized reciprocity norm as an adaptive strategy among lower-working class citizens."
石橋 伸恵 (北海道大学)
"Conformity or anti-Conformity?: Producer-scrounger behavior in group performance"
三船 恒裕 (北海道大学)
"In-group trust and in-group favoritism in a dictator game."
森本 裕子 (京都大学)
"Effects of trust on sanctioning behavior and evaluating self-fairness: Warning and Vengeance."
守谷 順 (東京大学)
"Impaired attentional disengagement from anger faces in social anxiety." 
大園 博記 (京都大学)
"Deception and cooperativeness: Evidence for counter strategy of free riders."
佐藤 嘉倫 (東北大学)
"Trust and social mobility: An empirical study of the effect of job change on trust."
敷島 千鶴 (慶応大学)
"Genetics and environment contributing to individual differences in socialization."
高橋 雄介 (東京大学)
"An attempt to measure temperaments of Gray’s reinforcement sensitivity theory experimentally."
高橋 伸幸 (北海道大学)
"Which is more important for the emergence of indirect reciprocity: Regarding giving to free-riders as “bad”, or regarding not-giving to free-riders as “good”?"
田村 亮 (北海道大学)
"Fear may be transferable across individuals: A psycho-physiological experiment."
森 久美子 (関西学院大学)
"Bargaining by children with autistic spectrum disorder."
品田 瑞穂 (北海道大学)
"Direct and indirect effect of punishment in the social dilemma."
山本 真也 (京都大学)
"Factors influencing reciprocity in chimpanzees."
特別講演 (16:00-18:00)
Leda Cosmides (カリフォルニア大学サンタバーバラ校)
"Cognitive adaptations for social exchange."
 
社会的交換は人間特有のものであり、人間はそれに関わる推論プロセスを適応の結果獲得してきたと考えられる。つまりそれは、祖先が直面してきた適応課題(例えば相互協力を達成するために、どのようにしたら裏切り者を見つけることができるか)を解くために獲得してきたプロセスである。発表では、裏切り者検知に焦点を当てた一連の実験結果について報告された。例えば、4枚カード問題において、一般的な文脈で正しく回答できたのはたった参加者の約1/4であったが、社会的交換に関する文脈では参加者の3/4以上が正しく回答できた。そして一連の研究では、この推論プロセスは領域限定的であり、一般的な推論とは異なる神経的基盤を持っていること、文脈がどの程度典型的であるかにかかわらず、社会的契約を含む限り生じること、さらに通文化的に見られる現象であることが示唆された。
レセプション (18:40-21:00)
 
第2日目 2006年9月10日(日)
講演2 (09:30-10:30)
山岸 俊男 (北海道大学)
"Culture and
institutions."
 近年文化心理学で報告されてきているような文化固有の行動パターンは、文化心理学者の主張するような共有された意味システムの反映ではなく、制度固有の適応戦略、つまり、人々はあるパターンの行動を引き起こす誘因構造を集合的に作ってきており、その誘因構造が自己維持的であるが故にそのようなパターンの行動は安定して見られるという「制度アプローチ」の観点から説明できる。発表では、制度アプローチの例として、これまで行われてきた一連の一般交換および内集団ひいきに関する研究が報告された。さらに発表では、最近行われた日本・中国・台湾における接合文化実験について紹介され、日本では中国、台湾と比較し、内集団ひいきが小さかったが、その一方で内集団における規範の逸脱者に対して罰する傾向が強いといったような文化差が生じていた。
近年文化心理学で報告されてきているような文化固有の行動パターンは、文化心理学者の主張するような共有された意味システムの反映ではなく、制度固有の適応戦略、つまり、人々はあるパターンの行動を引き起こす誘因構造を集合的に作ってきており、その誘因構造が自己維持的であるが故にそのようなパターンの行動は安定して見られるという「制度アプローチ」の観点から説明できる。発表では、制度アプローチの例として、これまで行われてきた一連の一般交換および内集団ひいきに関する研究が報告された。さらに発表では、最近行われた日本・中国・台湾における接合文化実験について紹介され、日本では中国、台湾と比較し、内集団ひいきが小さかったが、その一方で内集団における規範の逸脱者に対して罰する傾向が強いといったような文化差が生じていた。
講演3 (10:40-11:40)
Joseph Henrich(ブリティッシュコロンビア大学)
"Cultural learning,
institutions and the coevolution of human sociality."
 
発表では、人間の社会性の理解をいかにして進めるかについて、現時点での進化生物学、人類学、行動経済学、社会心理学などの学問分野の最先端の動向を紹介しつつ、新たな展開の可能性について議論された。まず、自然淘汰による考え方が紹介され、それにより人間の社会行動(誰と社会的交換を行うか、N人集団での相互協力はいかにして維持されるか、等)の一部分は説明可能だが、それでは全てを説明するには到底不十分であることが指摘された。なぜなら、その考え方は人間以外の生物種にも適用可能であり、人間社会の複雑性を説明するには至らないからである。そこで、人間固有の要因として、文化的学習能力、即ち模倣が想定される。模倣能力は情報探索コストを大幅に軽減できるため、適応的であり、これにより様々な規範や制度が均衡状態として成立可能となる。しかし、ここまでの段階では、複数均衡がモデル上存在し得るため、進化の過程でどこからスタートするか、また共貧状態からいかにして脱出するかという問題が残ることが指摘された。これを解決するためには、文化的集団淘汰を導入する必要がある。これは、うまくいっている集団における規範や制度が他集団に広まることであり、実験室及びフィールドでの知見が蓄積され始めていることが紹介された。そして最後に、文化的集団淘汰により遺伝子=文化共進化が実際に生じてきた可能性もあることが示唆された。
ポスター発表#2 (11:40-12:40)
明瀬 美賀子 (北海道大学)
"Cultural differences in attention: Comparing context sensitivity between Japanese
and Western subjects."
David Dalsky (北海道大学)
"Mutual enhancement in the United States and Japan."
林 治子 (東京女子大学)
"The perspectives of “good life” in Japanese retirees."
今井 真理 (立命館大学)
"The effect of art therapy on behavioral psychological symptom for people with dementia."
菅 知絵美 (東京女子大学)
"The structure of happiness among Japanese."
唐澤 真弓 (東京女子大学)
"Culture and well-being."
キム ジユン (東京大学)
"Content and implications of Japanese’ meta-stereotype of Koreans."
小宮 あすか (京都大学)
"Cultural and interpersonal aspects of regret."
丹羽 空 (九州大学)
"A regional cultural difference on telling “exaggerating” blunders."
大江 朋子 (東京大学)
"Dominant effect of affection in stereotype activation."
大沼 進 (北海道大学)
"Acceptance of a high cost sanction system: Why decision by discussion is preferred."
大野 秀実 (北海道大学)
"Depressive mood and discounting delayed monetary gains and losses."
ジョアンナ シュグ (北海道大学)
"Similarity attraction, relationship mobility, and actually selecting similar others: How social structural differences between Japan and the United States affect interpersonal similarity."
渋谷 和彦 (独立行政法人 理化学研究所)
"Beyond the differences: Ubiquitous jigsaw method for collaborative learning."
清水 裕士 (大阪大学)
"A study of normative conflict resolution strategies in Japanese culture."
高岸 治人 (北海道大学)
"The effect of dictator’s intentions in the third-party punishment."
高橋 知里 (北海道大学)
"Trust and punishment in three societies: A “joint-cultural” experiment in Japan, China, and Taiwan."
内田 由紀子 (甲子園大学)
"How culture shapes emotion? Emotion inference and expression in the United States and Japan."
講演3 (14:10-15:10)
Shinobu Kitayama(ミシガン大学)
"Voluntary settlement
and the spirit of independence."
 
発表では、「経済的に動機づけられた自発的移住」に独立的自己観の起源があるとする仮説を検討するために、相互協調的自己観が優勢であるとされる文化にありながら、北米と同様の「自発的移住」の歴史を持つ北海道に焦点を当て、北海道生まれの北海道在住者、本州生まれの北海道在住者、本州生まれの本州在住者、北米のアメリカ人に対し、感情経験、認知的不協和、原因帰属の実験を行った結果が紹介された。この自発的移住仮説と一致し、北海道生まれの北海道在住者の傾向は、ほぼアメリカ人における傾向と同様であった。さらに、本州生まれの北海道在住者の傾向は、自己選択が関連している感情経験、認知的不協和においては、アメリカ人と同様の傾向であったが、行為主体に関する素朴理論が関連している原因帰属では、本州人と同様の傾向であった。このことからこうした素朴理論は、その環境において生育することで徐々に獲得されていくものであることが示唆された。
講演4 (15:40-16:40)
Mary C. Brinton(ハーバード大学)
"Analyzing choices
and preferences during rapid institutional change: Young people in the Japanese
labor market."
 
文化と制度は密接に絡み合っているものであり、それが変化した際、人々の行動にどのような影響が生じるのか、人々にとってその変化に応じた行動をとるのは難しい(またはやさしい)のだろうか、そしてどのような個人にとってそれはたやすく、どのような個人にとって難しいのだろうか。発表では、90年代前半における日本の労働市場の変化に注目し、製造業の仕事が減少し、低学歴者が仕事に就けなくなったのに対し、数多くの中高年労働者に対しては依然として旧来の雇用制度が適用されているために、20代後半〜30代前半の若年層においては、高学歴でない限り正規雇用されない現状が報告された。そしてそのような変化において、日本の若年層はそのような環境の変化に応じたストラテジーを持つ必要性があるにもかかわらず、日本においては旧来のシステムに沿った「あるべきライフコース」が一種の規範として強くあり、それに逆らうのが難しいため、今のところそれが非常に困難であることが指摘された。
コメンタリー (16:50-17:10)
Yoshihisa Kashima(メルボルン大学)
Commentary
 
総合討議 (17:10-18:00)
シンポジウム終了 (18:00)
ワークショップ一覧
ページのTOPへ
|


